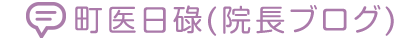
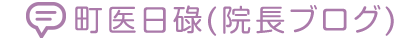
「町医日碌」と題して町医者の日記を随時掲載しております。
 私が医学生〜研修医であった1980年代まで癌はたとえ早期でも患者に告知しないことが一般的でした。
私が医学生〜研修医であった1980年代まで癌はたとえ早期でも患者に告知しないことが一般的でした。
例えば胃癌は家族には説明しても本人には胃潰瘍と言い続けました。
早期胃癌であれば治癒しますが、進行癌で切除不能であった場合などは有効な化学療法が乏しい時代でしたので、胃潰瘍という良性の病気の説明なのに病状は悪化するばかりで、患者は疑心暗鬼となり医師や家族に不信感を抱きながら亡くなるというケースが多くありました。ネットであらゆる情報が瞬時に手に入る現在では有り得ない、見え透いたウソが「癌の告知」に関しては許された時代でした(現在でも政治家や高級官僚は見え透いたウソをついておりますが)。
90年代に入りinformed consent(説明と同意、病状を全て説明し治療に際して同意を得ること)の概念が広がり患者本人に、たとえ手遅れの状態でも病状をつつみ隠さず説明することが一般的な時代になり、わたしも辻褄の合わぬウソを突き通すことから解放されてホッとした覚えがあります。
D子さんは60歳代でした。50歳代で献血されたときに偶然C型肝炎に感染していることが判明し、かかりつけの医師へ通院しておられましたが、わたしが勤務していた病院に来られた時には既に肝硬変に進んでいたことでC子さんには、当時唯一の治療法であったインターフェロンも使用できず肝庇護療法しかできませんでした。
やがて肝細胞癌が発生し肝動脈塞栓療法を繰り返すことになりました。
癌の発生から約6年後主治医の転勤に伴いD子さんはわたしの担当になりましたが、肝硬変はさらに進行し肝細胞癌の治療は不可能な状態で、症状の緩和が治療の目標となっていました。肝不全の進行に伴い腹水がおなかにたまりそのコントロールのための入院が増えて来ました。
そんなある日、病状の説明を求められたわたしは現状を詳しく説明しました。
D子さんは教職を長く勤められ、退職後は大学院で学び心理学の学位を得られたという聡明で、とても上品な女性でしたがわたしの辛い説明に動揺することなく「わかりました。苦痛はできるだけとってください。不要な延命処置だけは絶対にしないでください」とおっしゃられました。
その数ヶ月後、D子さんは肝不全で亡くなられました。わたしは約束通りに延命処置はせずに鎮静剤でできるだけ苦痛のないように努めました。
D子さんが亡くなられて数ヶ月後、同じく教育者であられたご主人が追悼文集を編まれ、送っていただきました。
教職にあられたので多くの教え子やご友人の方の追悼文に改めてD子さんの高潔な人柄を知ることができたのですが、 その中で主治医の転勤でわたしが担当した頃について「妻は主治医の突然の転勤を知らされた時にはかなりのショックを受け、全くタイプの異なる新しい主治医、三村先生にはしばらくなじめなかたようです。」とあるのにわたしがショックをうけました。が、続いて「しかしまもなく、癌治療に対するこの方の判断や技量の正確さが素人なりにも信頼できるようになり、事実そのようになりました。」とあって安心しました。
そしてD子さんがパソコンの中に残していたメモ書きも収録されており、わたしの説明について
「夜、三村先生から話を聞く。
1.ガンの勢いが強い。
2.腹水は四〜五リッター、利尿剤は効果ないだろう。
3.腹水が多すぎるためガンの治療は不可能
4.余命は年単位ではない。
5.腹水を取り出し、必要な栄養をまた体内に入れるとのこと。
もう覚悟はできているのでなるべく無理な治療はしないで(アツカマシイ!?)
それまで自分でできることは穏やかな気持ちでしたいと思っている。」
と書かれていました。
他の項では 「嘘でもよいから・・ 癌の末期は過酷な苦痛のもとに心も体もぐちゃぐちゃになってしまうと聞いている。私は嘘でも幻想でもよいから、心だけは透き通った状態でありたいと思っているのだけど・・。」
ともありました。
多くの末期癌患者を担当し、告知が一般的になってからは本人にとって寿命を区切るような辛い話を何度もしてきました。
多くの患者さんはいったん落ち込んでも前向きに受け入れていただきましたが、そのままふさぎ込んでしまう方もおられ、告知の是非を悩むこともありました。その中でD子さんほど自己の置かれた状況を客観的に判断し従容として運命を受け入れた方は極めてまれです。
また告知後の患者さんの本音を知る機会は実はあまり多くありません。
D子さんの追悼文集で、患者さんにとって、病名や余命の告知の重さを改めて認識させられたわたしは、その後、より丁寧に説明するように心がけるようになりました。
著者:みむら内科クリニック 院長 三村 純(みむら じゅん)
