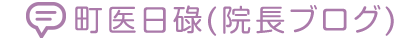
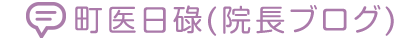
「町医日碌」と題して町医者の日記を随時掲載しております。
私が医師になって3年目の1990年、秋のことです。
患者さんは89歳の男性(Aさんとします)。食欲不振が続き、かかりつけの先生から紹介されて来院しました。
いくつかの検査で膵臓癌と判明しましたが、既に全身に転移がある状態でした。
現在のように多くの抗癌剤による化学療法もない時代で、まだ癌であることを本人に告げないことが一般的でありましたので本人には「慢性膵炎」と説明し、ご家族には「手遅れの膵臓癌で数ヶ月の余命」と説明していました。
Aさんは僧籍のある方で、大変穏やかな人柄の、人格者という雰囲気の人でした。
私はまだ20歳代でAさんにとっては孫にあたる世代であったからでしょうか、駆け出しの新米医者で若造の私が部屋へ伺うと、それこそ孫をみるような優しい視線で迎えてくれました。
手の施しようのない状態でしたのでAさんには、しばらく様子をみましょうとお話し、退院していただきました。
ご家族には新年を迎えられるか微妙な状況と説明しておりましたが、幸いにも小康を得られ、最後となったお正月をご家族ですごされました。しかし1月の半ば頃、外来に来られたAさんは衰弱され「先生、食べてもすぐに戻すんや」と力なく言われました。膵臓癌が十二指腸へ浸潤し腸閉塞を生じたのでした。
現在ではこのようなときに閉塞した腸管にステントという金属製の筒を留置することで一時的に症状を緩和するこが可能ですが、当時はそのようなものはなく鼻から胃へチューブを通して、貯まった胃液を抜くことしかできませんでした。
救急で入院していただき、鼻からチューブを挿入しましたが、それ自体苦痛を伴う処置なのにAさんは「先生に任せるわ」とだけ言われ、貯まった胃液を排出後は「ああ、先生のおかげで楽になったわ」といつもの優しい視線に戻られました。
その頃、私は外来以外の日は、当時西区の郊外にあった神戸市立玉津病院に出向し肺結核の患者さんを担当していたためAさんの主治医は別の先生にお願いすることになりました。
2月の始め、日曜日の早朝、おそらく5時頃だったと記憶していますが電話のベルが鳴り、あわててでたところAさんの入院している病棟からでした。昨夜からAさんの全身状態が悪化している、本人がもう一度三村に会いたいと言われている、とのことでした。出向中も時々様子を伺いに行っておりましたのでAさんの病状が悪化していたことはわかっていましたから、身支度をして急いで病室へ向かいました。
 早朝にも関わらず、部屋には多くのご家族が集まっておりました。
早朝にも関わらず、部屋には多くのご家族が集まっておりました。
私がベッドの横に立ったとき、Aさんの長女さんが「お父さん、三村先生よ」と呼びかけました。その時です。それまで酸素マスクをつけて、あえぐ様な呼吸をされていたAさんはパッと目を開け、私をみて、本当に嬉しそうな、気持ちの良さそうな、崇高な、という表現があてはまる笑顔をみせてくれました。
肺に水のたまったAさんから言葉は出ませんでしたが、「お前、来てくれたんか、嬉しいで〜」と思っていただいたのかもしれません。
私はAさんの手をそっと握りしめて一礼し部屋を辞しました。その日の夕方、Aさんはこの世を去られました。
勤務医の期間中、私の受け持ち患者の大半は癌患者でした。
特に若い頃は受け持ちの十数人全員が癌患者であったこともあります。そして、これまでに100人以上の方のご臨終に立ち会い、見送ってきました。
その中でAさんが最後に見せてくれた笑顔が今も私の脳裏に焼き付いて離れません。あの時のAさん以上の笑顔にその後は会えていないのです。
そして、あの笑顔に会えた時に初めて「この仕事を選んで良かった」と思いました。
著者:みむら内科クリニック 院長 三村 純(みむら じゅん)
