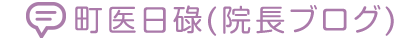
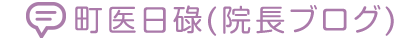
「町医日碌」と題して町医者の日記を随時掲載しております。
今から36年前の1987年にわたしは大学を卒業し研修医になりました。
勤務の始まる数日前に開業医だった父から「これを読んでおけ」と一冊の本をわたされました。
「正直な誤診のはなし」というタイトルの本で、臨床医の著者が長年の経験からどのような時に誤診に至りやすいかを率直で具体的に述べてあり、その一節に「患者に腹を立てている時に注意」というお話がありました。詳しい内容は忘れてしまいましたが読んだ時は「そんなものか〜」と思っただけでした。
研修医で勤めた病院は神戸市で当時唯一の三次救急までを扱う病院でしたので救急外来は患者があふれて連日文字通り野戦病院のような状態でした。なので一年目の終わり頃になりますと経験もつみ、重症患者の対応にも慣れてきて慌てふためくことも減ってくるのですが、そんなある日の昼下がり、わたしは前日の朝から連続32時間勤務で救急外来におりました。
前夜も忙しく一睡もできなかったので疲れはピークですが気分は何故かハイになっていたかもしれません。すると消防局からのホットラインが鳴りまして救急搬送の依頼です。

「21歳の男子大学生、頭痛から意識障害、バイタルサインは安定」とのことで受け入れOKと答えましたら「中央区のホテル○○から約10分で到着」といわれました。すると同僚の研修医たちが「おい、ホテル○○てラブホやで」「そうやそうや」「月曜の昼間からラブホにしけこんでるんか」「意識障害て、なんか薬でもやってるんちゃうか」などと好きなことを言ってると救急車が到着、ストレッチャーに乗せられた男性は一見元気そうですが「ここは何処や〜、俺を殺すんか〜」と叫んでいます。
「名前言うて」と聞くと「知らん」と何を聞いても会話にならない状態で、酒の臭いはしませんがラリってるようにもみえました。そこでわたしが「ちょっと、あんた、なんか薬やってんのちゃう?」と聞いてみたところ「クスリぃ?やってるよ〜」と。
「やっぱりやこいつぅ」「しゃ〜ない奴っちゃな〜」「目が覚めたら帰そうぜ」とだんだん腹が立ってきました。そこでホテルから付き添って来た彼女に聞きました。
「あんたたち、なんか薬とかやってたんじゃないの?」と今から思えば失礼を通り越して全く無礼なことを言ってしまいましたが、彼氏の急変に顔面蒼白だった彼女は「そんなことは絶対にしていません、お酒も一滴も飲んでいません。彼を助けてください」と涙ながらに訴えます。その真摯な訴えにウソはなさそうで、「おい、なんかおかしいぞ」「CTは撮らなあかんな」と同僚と決めてわたしがCT室まで同行しました。
患者は不穏状態でしたので暴れて台から落ちてしまわないように撮影中もすぐ横で状態を観察していました。現在の機器では頭部のCTはほんの数秒で画像化されますが、当時は数分かかりました。するとモニターを見ていた放射線技師がマイク越しに教えてくれました「ザーがあるわ」「ええっ〜」
ザーとは業界用語でくも膜下出血のことを言います。英語でSubArachinoid Hemrrageの頭文字SAHをドイツ語読みしたものです。これは命に関わる緊急事態です。すぐに救急外来に戻り「えらいこっちゃ、ザーや」「なにぃ..ほんまか」「この歳で?」とみんなで驚きながら脳神経外科医に連絡、直ちに脳血管造影が行われ、脳外科の先生もそれまで経験のなかった巨大な動脈瘤が確認され、そして緊急手術となり一命を取り留めました。
 結果的に誤診には至りませんでしたがあのまま放置して無理矢理帰宅させたりしていたら取り返しのつかないことになったに違いなく、患者に腹を立てていると誤診しやすいとはこういうことかな、と思いました。
結果的に誤診には至りませんでしたがあのまま放置して無理矢理帰宅させたりしていたら取り返しのつかないことになったに違いなく、患者に腹を立てていると誤診しやすいとはこういうことかな、と思いました。
それ以降どのような症例にも先入観をもつことなく対応するようになったわたしですが、あのとき診断確定後バタバタしていて、一緒だった彼女のことは忘れてしまいました。向こうももう忘れているかもしれませんが「失礼なことを言ってしまい申し訳ございませんでした」ともしもお会いすることがあれば伝えたいとずっと思っています。
新年あけましておめでとうございます。この拙いブログをお読みくださる皆様に2023年が良き1年となりますよう心からお祈りいたします。診察中、ブログ読んでますよ、と仰っていただくことが最高に嬉しいわたしです。
著者:みむら内科クリニック 院長 三村 純(みむら じゅん)
